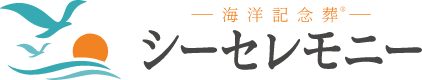墓じまいとは、既存のお墓を撤去することです。その性質上、人生において何度も経験するものではありません。そして、墓じまい後の供養方法についても、身近に相談できる人はなかなかいないため、分からないことが多いという方がほとんどではないでしょうか。
しかし、最近ではさまざまな事情から墓じまいをする人が増えてきました。そこで今回は、墓じまいとは具体的にどのようなものなのかについて解説します。
さらに、多くの方々がご遺骨の供養先として検討する、海洋散骨や永代供養、納骨堂などの墓じまい後の供養方法についても詳しく紹介するので、ぜひ参考になさってください。
目次
「墓じまい」とは?

墓じまいとは、敷地内にある墓石を片付けて更地の状態に戻した後、お寺や墓地の管理者に返還することです。別の場所にご遺骨を移転させることから、「お墓のお引越し」や「改装」とも呼ばれています。
しかし、墓じまいはただ墓石を撤去するだけではなく、お墓から取り出したご遺骨の管理についても、併せて考える必要があります。
この項目では、墓じまいをするにあたって注意したいポイントを解説します。
自分に合った管理方法を選ぶ
これまでは、ご遺骨の管理といえば、お墓への納骨が大半を占めていました。しかし、近年ではご遺骨の管理方法にはいくつかの選択肢があり、ライフスタイルや価値観、費用などによって最適なものを選べます。そのため、無理なく管理ができる方法を選ぶのが得策です。
墓じまいをしてしまうと、ご遺骨を元の状態に戻すことはできなくなります。したがって、無計画に墓じまいを進めるのではなく、今後どのように供養をしていくのかをしっかりと決めてから墓じまいを実行することが大切です。
墓じまい前に親族間でしっかりと話し合う

先祖代々守られてきた大切なお墓だからこそ、供養方法は人それぞれだといえます。特に、ご高齢の方のなかには、墓じまいに対して良い感情を持っていない方も少なくありません。そのため、自分一人で墓じまいを決断せず、親族の皆さんと事前に話し合い、しっかりと承諾を得ておくことが大切です。
墓地管理者に相談する

親族間で了承を得られた後は、いよいよ墓じまいを行うことになりますが、そのためには現在お墓のある寺院や霊園の管理者に「埋葬証明書」を発行してもらわなければなりません。「埋葬証明書」を市町村の役場に提出することで、「改葬許可証」を発行してもらえます。
寺院や石材店とのトラブルを回避
唐突に墓じまいの話を進めてしまうことによって、長年に渡って檀家となっていた墓地管理者である寺院と離檀料を巡ってトラブルになるケースもあります。そうならないためにも、寺院側と事前に相談し、墓じまいへの理解を得ておきます。
また、墓石を撤去するには石材店に依頼をする必要があります。近年では、撤去料やサービスに関するトラブルも起こっているので、事前に数社から見積もりを提出してもらう対策が必要です。
墓じまいで起こり得るトラブルの詳細記事はこちら
墓じまいを検討する方が増えている時代の背景

近年になって墓じまいを検討する方が増えていることには、いくつかの理由があります。
後継者不足
少子高齢化が進み、先祖代々のお墓を守っていく後継者がいないため、自分たちが元気なうちに墓じまいをするという方が多くいます。
お墓参りや管理が困難
たとえ後継者がいたとしても、生活圏とお墓の場所が離れ過ぎていると、お墓参りに行くことも困難です。また、お墓周りの清掃や修繕といった管理も、遠方に住んでいると難しくなります。
お墓の維持管理費の負担が大変
霊園や寺院にあるお墓は、毎月管理料を支払います。そういった維持管理費は、お墓がある限り半永久的に必要となるため、子供や孫などこれからの世代にお墓のことで負担をかけたくないという思いから、墓じまいをするケースも多くあります。
お墓に対する考え方の変化
以前までの日本において主流だった、「死後は先祖代々のお墓に入るもの」といった考え方が薄れ、お墓そのものを必要と感じない方が増えてきたのも、墓じまいが頻繁に行われるようになった原因の一つです。
墓じまい後の遺骨はどのように供養するのか

墓じまいを行ったときに取り出したご遺骨の供養方法として、いくつか選択肢が挙げられます。どれが正解というものではなく、親族間でしっかりと話し合いを行い、全員が納得できる方法を選ぶことが大切です。
この項目では、墓じまい後の供養方法として代表的な四つの方法について紹介します。どのような選択をするにしても、お墓から遺骨を取り出す際には市区町村の役所にて改葬許可証の交付を受ける必要がありますので、遺骨を取り出す前に行政で手続きを行ってください。
管理の手間がかからない「永代供養(合葬・合祀)」

永代供養とは、お墓の管理から供養までを全てお寺に任せられる供養方法です。
将来的に管理の手間がかからないことにメリットを感じて選択する方が多くなっています。
経済的負担が軽い
永代供養では、これまでのお墓のように年間の管理料が発生しないところがほとんどです。管理や供養に関する費用を最初に支払うことで、その後の供養に掛かる負担を大幅に抑えることが可能です。
交通アクセスが良い場所にある
永代供養墓はアクセスが良い場所にあることが多く、一般的なお墓に比べて供養場所へ行きやすいのが特徴です。
一度納骨すると、再び取り出せない場合も
永代供養のなかには、血の繋がりのない方のご遺骨と一緒に埋葬を行う、合葬・合祀型という供養方法があります。一つの大きなお墓に数多くのご遺骨を納骨するため、一度納骨をしてしまうとその後はご遺骨を取り出すことができないので注意が必要です。
永代供養の詳細記事はこちら
一人ひとりのお墓を確保できる「納骨堂」

永代供養の合葬・合祀型のように、血の繋がりのない他の方のご遺骨と一緒にするということに抵抗がある方や、より身近なところで供養したいという場合に選ばれているのが納骨堂です。
納骨堂は骨壷のまま収蔵する供養方法で、永代供養費のほかに維持管理費を定期的に支払い続ける必要があります。
さまざまな種類がある納骨堂
納骨堂には、ロッカー型や仏壇型などさまざまなタイプがあります。最近では、ビジネス街にあるようなビルの内部が、納骨堂となっているケースも多くなっています。
納骨堂は利用期間を決めて申し込みをすることが一般的です。期間は三回忌や三十三回忌、五十回忌などの法要の節目に合わせてあることが多く、その後は共同のお墓で合葬されます。
運営母体によって異なるシステム
納骨堂を運営している主な母体として、寺院・地方自治体・民間法人の3つがあります。特に、寺院が運営母体の場合、その寺院の檀家になることが利用条件となっているケースあります。運営母体によってサービス内容や費用に大きな違いが生じるのも、納骨堂の特徴です。
納骨堂の詳細記事はこちら
自宅で手間をかけずに管理できる「手元供養」

手元供養とはご遺骨を自宅で保管しながら供養する方法です。
永代供養や納骨堂と違って他者が介入しないため、規約にとらわれず自由に供養ができます。
いつも身近に故人を感じられる
手元供養の一番のメリットは、いつでも故人を身近に感じられることです。お墓参りに出かける必要がなく、いつでも好きな時に自宅で供養をすることができます。供養品を購入するのに費用が発生しますが、それでも通常のお墓に比べて経済的な負担を大幅に抑えられます。
また、外出先でも故人を身近に感じていたいという方は、ご遺骨を加工してアクセサリーとして身につけるといった手元供養も選択できます。
遠い将来の供養も考慮する
現在、手元供養をしている自分自身に何かがあった場合など、半永久的に手元供養を続けるのか、あるいはほかの供養方法を選択するのかといった、遠い将来の供養方法についてもしっかり計画を立てておく必要があります。
手元供養の詳細記事はこちら
近年人気になってきた海や山への「散骨」

多様化する葬送方法のなかでも、近年注目されているのが自然散骨です。
散骨とは、「死後は自然に回帰したい」といった、自然と一体化することを希望されている方が注目している、海や山へご遺骨を散骨して供養する方法です。
場所による散骨の違い
ご遺骨を撒く場所によって、散骨の方法やマナーにも違いが生じます。例えば、散骨のなかでも一般的な海洋散骨の場合、散骨ができる海域まで船をチャーターして向かいます。
山への散骨は海とは違って、必ず所有者がいるため、散骨の許可を取る必要があります。しかし、個人で許可を取るのは難しいため、海洋散骨も山への散骨も専門業者に依頼をするのが得策です。
費用を大幅に抑えられる
お墓を持たない供養方法である散骨は、専門業者への依頼料は必要となりますが、一度散骨を終えたら、その後の費用は一切発生しません。そのため、長期的な目で見ても永代供養や納骨堂利用よりも大幅に費用を抑えることができます。
散骨には粉骨作業が必須
散骨を行う場合、元のご遺骨の形が分からないように一片を2ミリ以下まで砕く、粉骨作業が必要となります。こちらも専門業者に依頼することで費用が掛かりますが、散骨と粉骨をセットで取り扱っている業者も多いようです。
散骨の詳細記事はこちら
シーセレモニーで執り行う海洋記念葬

シーセレモニーでは、ご遺族の思い出に残る海洋散骨セレモニーを行っております。ご遺族様のみで散骨を行う『ファミリー散骨』とスタッフが代行して散骨を行う『代理散骨』の二つのプランを用意しています。また、シーセレモニーでは散骨プランだけではなく、手元供養品も数多く取りそろえています。ご遺骨の一部だけを散骨し、残りを手元供養で管理するといった方にもおすすめです。

ご自宅の仏壇に置いておけるような小さな骨壷タイプ、身につけるソウルジュエリーなど多数ご用意していますので、ご希望の場合はお気軽にご相談ください。
散骨に関する注意点

散骨プランでは、ご遺骨を「粉骨」する必要があり、費用は30,000円(税別)です。ただし、遺骨の状態によっては粉骨前に洗浄や乾燥を行うことがあり、その際には別途料金がかかります。そのため、お引き取りの際に遺骨の状態を確認させていただきます。
粉骨プランはこちら
海洋散骨の実績

ここでは、実際にシーセレモニーの散骨プランをご利用いただいたお客様の散骨エピソードをご紹介します。
個別散骨/ファミリー散骨

- クルーザー:アニー号
- プラン:個別散骨/ファミリー散骨
- 乗船人数:3名
- 散骨場所:東京湾
こちらのお客様は、3名で個別散骨/ファミリー散骨を行っていただきました。天候にも恵まれ、穏やかな東京湾で故人様をお見送りされました。
「お客様の声」を紹介
先日はありがとうございました。母も喜んでいました。
海が大好きだった父も喜んでいるかと思います。
大変お世話になりました。
個別散骨/ファミリー散骨の実績詳細はこちら
ご遺族様が安心できる選択を

近年、時代とともに変わっていく家族の形に合わせるように供養方法も多様化しています。墓じまいの後、故人様をどのように供養していくのか、将来的な費用や供養をしていく方はもちろん、お墓に関わりのある親族のみなさまの思いも踏まえてきちんと話し合わないと、後々トラブルを引き起こす原因となってしまいます。
供養方法で迷っている方、経済的な不安を抱えている方も含めて、シーセレモニーの海洋記念葬にご相談ください。専門コンシェルジュが、ご遺族様の希望に沿った散骨プラン作成のお手伝いをいたします。
海洋記念葬についてはこちら