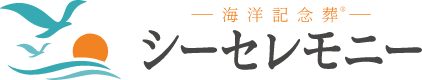散骨は故人様のご遺骨を自然に還す葬送方法の一つとして、近年注目を集めています。しかし、海や山ならどこにでも散骨してよいわけではありません。
これから墓じまいをして散骨をしようとお考えの方は「具体的にどこに散骨できるのか」「散骨の際にどんなことに気をつければよいのか」など、分からないことも多いのではないでしょうか。
そこで今回は、散骨を検討している方に向けて散骨の種類や注意点などについてお伝えします。
目次
海や山へご遺骨を撒くのは違法ではない

海や山へ散骨することは法律的に大丈夫なのか心配される方は多いです。
現在の日本には散骨を禁止する明確な法律は存在しません。1991年に「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪に該当しない」という法務省の見解に基づいて行われています。
したがって、「故人の供養のために常識の範囲内で」散骨を行うことは違法ではありません。山への散骨で注意しなければいけないのは、ご遺骨の上に土をかぶせたり埋めたりする行為です。これは「墓地、埋葬等に関する法律」により違法とされています。
散骨はあくまでも「撒く」ことであり、土をかぶせることは「埋葬」とされ、許可のある墓地や霊園でしかできませんので注意が必要です。
出典:e-Gov法令検索『墓地、埋葬等に関する法律』
散骨の種類
散骨には、以下の種類があります。それぞれの特徴を理解して最適な方法を選択しましょう。
海洋散骨

海洋散骨は、故人様のご遺骨を海に還す方法です。ご遺族が船をチャーターし、散骨可能な海域で行います。海岸や砂浜、漁場、養殖場周辺での散骨は禁じられています。ただし、土地の所有権の観点では山よりも寛容で、比較的場所を選びやすいというのも特徴です。
生前海が好きだった方や「死後は雄大な海に還りたい」と願う方に選ばれています。
里山散骨

里山散骨は、ご遺骨を里山に撒く方法です。樹木葬のように特定の場所に埋葬するのではなく、山に散布する方法です。
山には所有者がいるため、必ず許可を得る必要があります。山の所有者に自分で直接交渉するのは難しいため、散骨の専門業者に依頼するのが一般的です。ただし、自分の所有している山であれば自由に散骨ができます。
関連記事:里山散骨とは?種類と費用相場を解説
宇宙散骨

宇宙散骨は、故人様のご遺骨を宇宙空間に打ち上げて散骨する方法です。カプセルにごく少量のご遺骨を収めてロケットで大気圏外に打ち上げる方法や、バルーンにご遺骨を収め、高度30~35kmで破裂させる方法があります。
故人様が宇宙が好きだった場合、遺志を尊重しながら供養ができる魅力的な方法です。
散骨を希望する理由

近年、散骨を希望する方が増えていますが、その理由の一つとして「墓じまい」があります。墓じまいは、お墓を撤去して更地に戻すことです。少子高齢化やライフスタイルの変化などを理由に、墓じまいをしてその後散骨を選択する方が多くいます。
また、それ以外にも散骨を希望するのには、以下のような理由が挙げられます。
- 自然が好きである
- 家族や親族にかかる維持・管理の負担を減らしたい
- さまざまな事情でお墓に入りたくない
散骨の際に注意すること

散骨をする際には、以下の注意点があります。
家族や親族の了承を得る
ご遺骨を自然に還す散骨は、故人様のご遺骨が残らないことや墓石が存在しないことから、家族や親族に受け入れられにくいことがあります。散骨を自分だけで決断してしまうと「なぜ相談してくれなかったのか」と、あとから家族や親族と関係が悪くなってしまうこともあります。
そのため、事前に話し合いをしてから決定することが重要です。家族や親族に散骨の合意を得ることで、将来的なトラブルを避けられます。
ご遺骨が手元に残らないことを理解しておく
一度散骨されたご遺骨は、取り戻すことができません。あとになって「故人を身近に感じられなくて寂しい」「お墓を建てたい」などと思っても、ご遺骨が手元に残っておらず後悔する可能性があります。
対策としては、ご遺骨を分骨して一部を手元に残し、残りを散骨するという方法がおすすめです。
自治体のガイドラインに従う
現在の日本には散骨に関する明確な法律はないとお伝えしましたが、何もかもが自由にできるというわけではありません。
自治体によって散骨のガイドラインが定められている場合がありますので、ご自身がお住まいの地域や散骨を希望するエリアのルールを事前に確認しておくことが大切です。
粉骨する

散骨する前には、ご遺骨と分からないよう2mm以下のパウダー状にする「粉骨」が必須です。お墓に納骨されていたご遺骨は洗浄や乾燥が必要なため、専門業者に依頼するか、シーセレモニーでも承っていますのでお気軽にご相談ください。
平服で行う
通常の葬儀では喪に服す意味での喪服がマナーですが、散骨当日の服装は平服が適しています。周囲の方の心情を考慮して喪服は控えるのがマナーです。
また、海への散骨の場合、船に乗るため足元はすべりにくく安定性のある靴がおすすめです。
自然に還らないものは撒かない

海や山へ散骨する際には、環境に配慮するのがマナーです。献花は花びらのみを使用し、セロファンやリボンなど自然に還らないものはあらかじめ省いておきます。自然への感謝と敬意を持ちながら、故人様との最後の別れを行うことが大切です。
納得できるまでじっくり考えることが大切
お墓の継承者がいないことや経済的な負担が少ないなどの理由から人気が高まっている散骨。しかし、散骨してしまうとご遺骨は手元に戻ってこないため、家族・親族の皆様が納得できるまで話し合いを重ねることが大切です。
全てを散骨するのではなく、分骨した一部を手元供養として残すことも可能です。手元供養品についてのご質問も承っておりますので、シーセレモニーまでお気軽にご相談ください。