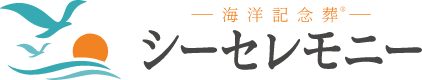先祖代々続くお墓は、家族や親族が定期的にお墓参りをすることで、きれいに手入れされた状態を保つことができています。実際に、お墓参りに行った際に荒れ果ててしまったお墓を見かけたことがある方もいるのではないでしょうか。
お墓がこのような状態になってしまうのには、さまざまな理由があります。そこで今回は、墓じまいをしないでいるとどうなるのか、そして無縁墓を防ぐための対策について解説します。さらに、近年注目を集めている「お墓を持たない供養方法」についても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
墓じまいしないとどうなる?お墓の管理先によって異なる対応

お墓の面倒を見る親族がいない、長い間放置され続けたお墓は「無縁墓」と呼ばれます。あるいは、寺院や霊園への管理料の未払いが続く場合にも同じく無縁墓として扱われるようです。
無縁墓になってしまった後の処遇はお墓の管理運営先によって違いがありますが、代表的な処遇としては以下が挙げられます。
無縁墓が公営墓地の場合
国や自治体が運営しているお墓の場合、無縁墓を撤去する費用は税金で賄われていることから、年間に撤去できるお墓の数や予算にも限りがあります。撤去できない無縁墓がそのままの状態で数年に渡って放置され続けることも珍しくありません。
無縁墓が民営墓地の場合
霊園のような民間企業が管理をしている墓地の場合、管理料の滞納がある程度の期間続くと即座に管理者によって撤去されます。
お墓が取り壊された後のご遺骨は、骨壷から出した状態でほかの人のご遺骨と一緒に供養される合祀墓(ごうしぼ)に移されます。一度合祀墓に移されると後からご遺骨を取り出すことはできません。
無縁墓が寺院の場合
民間墓地の対応と同じように墓石は撤去され、ご遺骨は合祀墓に移されます。しかし、寺院によってはあえて墓石を撤去せず、そのままの状態で放置するというところもあるようです。寺院にある墓地は寺院によって対応が全く異なるため、注意が必要です。
放置されるお墓がある理由

なぜ無縁墓が生まれてしまうのか、その理由はご遺族様の状況によりさまざまです。ここでは、代表的な理由を紹介します。
お墓を管理する後継者がいない
少子高齢化によって、将来的にお墓を管理する後継者がいなくなってしまったことが大きな理由の一つです。核家族化が進むことで「お墓を継ぐ=家を守る」という意識を持つ人々が少なくなったといえます。
墓守として定住できない
たとえ後継者がいたとしても、お墓の近くに住んでいないと日頃から管理をするのは難しいです。しかし、就職や結婚によって地元を離れて暮らす方が多いことからお墓を管理できずに放置してしまうケースも少なくありません。
維持費を捻出できない
民間の霊園の場合、月々や年間を通してお墓の管理料を支払う必要があります。さらに、定期的にお墓の修繕費や維持費も考えなければなりません。そういった費用が高額で支払えず、放置せざるを得なかったというケースもあるといいます。
無縁墓に罰則規定がない
お墓を放置した場合でも、一切罰則がないことも無縁墓が増えてしまう要因の一つでした。しかし、1999年の法改正により、墓地管理者によって撤去が行えるようになったため、民間の霊園の場合は無縁墓も少なくなりつつあるようです。
お墓があることを知らない
核家族化が進んだことが原因で自分の親族と交流がないという方も少なくありません。そのため、先祖代々のお墓というものがあることを認識できずに知らない間に無縁墓になっていたという場合もあるようです。
無縁墓にしない方法
お墓の継承者がいないことや、お墓の維持管理費といった経済的な負担の大きさが原因で無縁墓が作られてしまうというケースが増えています。
そういった場合には、どのような形でお墓を維持していくのか、無縁墓を作らない新たな供養方法を検討する必要があります。
管理しやすい場所へ改葬する

もし、お墓が遠方にあるために無縁墓になりかけている状態なら、お墓の改葬を検討してみてはいかがでしょうか。
改葬とは、簡単にいえばお墓を引っ越すことで、後継者が管理しやすい土地にお墓を建立します。改葬するためには、改葬許可証といった書類の準備や手続きに加え、閉眼供養や開眼供養の儀式を行います。
墓じまいを視野に入れる

後継者が見込めず、経済的にも維持管理が難しいという場合には、無縁墓になる前に墓じまいをする方法もあります。墓じまいとは、墓石などを撤去し、借りていた区画を更地にして管理者へと返還することです。墓石を撤去した後は、その下に納骨されていたご遺骨の今後について考える必要があります。
例えば、民間の納骨堂で永代供養してもらったり、自宅で手元供養したりなど、自分たちのライフスタイルに合わせた供養しやすい方法を選択します。
海洋散骨で供養

近年、注目を集めている供養の方法として「海洋散骨」が挙げられます。ご遺骨を細かい粉状に粉砕し、海に撒いて供養する方法で、死後は自然に還りたいと願う方に注目されています。お墓を持たない供養方法である海洋散骨なら、維持管理費がかからないというメリットもあります。
また、海洋散骨ではご遺骨のすべてを散骨する場合や、一部を残して永代供養や手元供養をする場合など、供養の方法を自由に選択できる点も人気の高い理由です。
無縁墓になる前にきちんと供養方法を考える

お墓は建てたら終わりというものではなく、長い間ずっと手入れをしながら維持管理しなければなりません。先祖代々から続く大切なお墓を無縁墓にしないためには、お墓の継承者が責任を持って管理することが大切です。
シーセレモニーでは、故人様やご遺族様に寄り添った海洋散骨のサービスを行っております。具体的にどういったサービスが受けられるのか、プランの実績内容をご紹介いたします。
ファミリー散骨プラン

- 使用クルーザー:ミッドブルー号
- 利用プラン:ファミリー散骨プラン
- 乗船人数:16名様
中型クルーザーのミッドブルー号を貸切にし、合計で16名様のご家族で散骨エリアとなる東京湾羽田沖へと向かいます。散骨エリアでは、故人様へのメッセージを書いたおくり鳩も一緒に散骨します。故人様のためにご家族様が持ち込まれたお酒も、献酒として利用可能です。
散骨セレモニーの後は、お食事プランも希望されていたので、船の後方デッキで雄大な海を眺めながらお食事を召し上がっていただきました。その後、桟橋へと戻ってプランの終了です。
ファミリー散骨プランの実績詳細はこちら
このほかにも、ご遺族様に代わってスタッフが散骨を行う代理散骨プランも提供しています。海洋散骨に興味を持たれましたら、シーセレモニーまでお気軽にお問い合わせください。