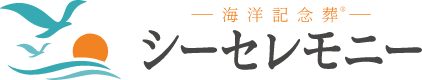火葬後のご遺骨は、通常骨壺に入れてお墓に収められますが、近年では、ご遺骨を分割して複数箇所に納骨し、供養するケースが増えています。特に散骨を希望される方が増えており、その際にご遺骨の一部を手元に残したいと考える方も多いのではないでしょうか。
このような場合に必要となるのが「分骨」です。分骨には、適切な手続きが必要で、この手続きを怠るとトラブルになる恐れもあるため十分注意しましょう。
今回は、分骨の流れや必要な手続き、シーセレモニーが行う海洋散骨について解説します。参考にして悔いのない供養の方法を選んでください。
目次
遺骨を分けて供養する分骨

分骨とは、故人様のご遺骨を複数の場所に分けて納骨し、管理または供養することです。ご遺骨をお墓やご自宅で管理する、もしくは海や山へ散骨するなど、その供養先はご遺族によって異なります。
もともとは、一つのお墓に埋葬されたご遺骨を複数の場所に分けて埋葬することを意味していました。しかし現在では、「ご遺骨の一部をほかの場所に納める」という広い意味で使われています。
分骨をする目的には、手元供養や散骨など供養方法の多様化、遠方のお墓への移動負担の軽減、故人様の自然回帰への想いへの配慮などが含まれます。
分骨の手続きについて

分骨のタイミングと方法には大きく2つのパターンがあります。1つ目は火葬場で分骨する場合、2つ目は納骨後にご遺骨を分骨する場合です。
それぞれ手続きや必要な証明書、費用が異なるため注意しましょう。
1.火葬場で分骨する場合

分骨を火葬場で行う場合は、事前にその旨を火葬場もしくは葬儀社に伝えておく必要があります。この際、分骨用の骨壺やペンダントなどの容器を用意するとともに、分骨先の施設に提出する「分骨証明書」も必ず受け取りましょう。
この証明書は、後に納骨する際に必要になるため大切に保管してください。なお、火葬の際に発行される「火葬許可証」とは異なるため注意が必要です。
2.納骨後に遺骨を分骨する場合

すでに納骨済みのご遺骨を分骨する場合は、納骨先であるお墓を管理する管理会社や寺院に依頼して日程調整を行い、お墓からご遺骨を取り出します。この際、故人の魂を抜くための閉眼供養(魂抜き)や、再び納骨する際に行う開眼供養(魂入れ)などを執り行います。これらの儀式には費用がかかることもあるため、事前に確認しておきましょう。
また、火葬場での分骨と同様に「分骨証明書」の発行を依頼し、分骨先の管理者に分骨証明書を提出します。分骨証明書の準備と納骨の手続きが済んだら、分骨先へ納骨します。
分骨にかかる費用
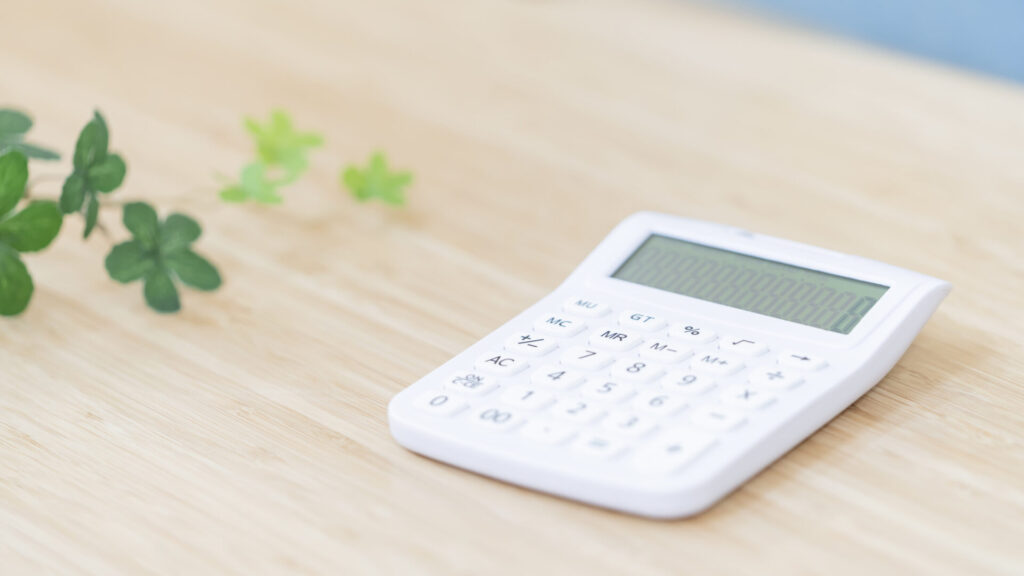
ご遺骨を分骨する際の費用は、「火葬場での分骨」と「納骨後の分骨」で異なります。それぞれの費用相場についてご説明します。
1.火葬場で分骨する場合の費用相場
火葬場で分骨する際に費用は発生するのは、分骨したご遺骨を入れる容器代・分骨証明書の発行手数料です。
- 容器代:小型の骨壺で3,000〜数万円
- 分骨証明書:100〜300円(自治体によって異なる)
分骨したご遺骨を入れる容器は、故人様の好きな色味の小さな骨壺やインテリアとして部屋に飾れる写真立てタイプなどさまざまです。アクセサリーとして身に着けられるものもあり、選ぶ容器によってかかる費用は変わります。
火葬場で分骨する場合は、分骨証明書を受け取りますが、分骨先が複数ある場合は、分骨先ごとに分骨証明書が必要になるため注意しましょう。
2.納骨後に分骨する場合の費用相場

納骨後の分骨では、容器代のほかに閉眼供養のお布施やご遺骨を取り出す費用、分骨証明書の発行手数料がかかります。
- 容器代:小型の骨壺で3,000〜数万円
- 閉眼供養のお布施:10,000〜30,000円
- ご遺骨を取り出す費用:20,000〜30,000円
- 分骨証明書:100〜300円
閉眼供養は、納骨された場所に宿っている故人様の魂を抜くための儀式で、僧侶に依頼して行うのが一般的です。僧侶に渡すお布施の金額は、依頼する僧侶や寺院、離檀料の有無などによって異なります。
また、お墓からご遺骨を取り出す場合は、作業を依頼する石材店へ支払う費用も発生します。
分骨したご遺骨の供養方法と注意点

分骨したご遺骨をどこに納骨し供養するか、または手元供養を選ぶかはご遺族によってさまざまです。分骨したご遺骨を供養する場合には、ご遺骨の取り扱いや供養方法についていくつか注意すべき点があります。
新たに埋葬する場合は、火葬証明書と分骨証明書が必要です。手元供養や散骨を選ぶ場合には証明書の提出は不要ですが、将来納骨する可能性を考えて証明書を発行してもらい、大切に保管しておきましょう。
分骨後の供養方法
分骨後の供養方法には以下のような選択肢があります。
- 新たな場所への納骨
- 自然散骨
- 手元供養
墓地や霊園、寺院に新たに納骨する場合は、必要な手続きや証明書の提出が必要です。事前に供養先の規則や条件を確認しておきましょう。また、海や山など自然にご遺骨を還す供養方法である散骨では、自治体の許可が必要な場合もあります。一方、骨壺を自宅で保管したり、アクセサリーや写真立て型の容器に納める手元供養では、特別な手続きは不要です。
供養する際の注意点

供養する際には、さまざまな注意点があります。
分骨証明書の保管
分骨時には必ず分骨証明書を発行してもらい、大切に保管しましょう。特に、将来的に納骨や改葬をする場合は、この分骨証明書が必要不可欠です。
家族間の同意
分骨や供養の方法について、家族や親族の間で意見が分かれることがあります。分骨後の供養方法に関してしっかり話し合い、納得する形にすることが大切です。
保管環境や供養先の確認
ご遺骨を自宅で保管する場合は、湿気や温度変化に注意が必要です。風通しがよく湿気がこもりにくい場所で保管しましょう。また、新たな場所に納骨する際には、適切な手続きを行うために事前の確認が大切です。一部の霊園や自治体が運営している公営墓地などでは、分骨後の納骨を禁止している場合があるので注意しましょう。
シーセレモニーの海洋散骨

シーセレモニーでは、分骨したご遺骨を海へ散骨できるファミリー散骨・代理散骨のプランをご用意しています。
ファミリー散骨プラン

ファミリー散骨プランでは、貸切のクルーザーに乗船し、故人様をお見送りいただけます。クルーザーの定員までであれば、何名様でも費用は変わりません。
散骨を行う際の献花や献酒など、故人様を供養するサービスが含まれています。また、ご遺族のご希望に合わせて海上で食事したり、故人様のお気に入りの音楽を流したりすることも可能です。
お食事のオプションは中型もしくは大型のクルーザー専用ですが、ぜひご遺族のみなさまでビュッフェやBBQスタイルのお食事をお楽しみください。ご家族やご親族とともに故人様を偲ぶ貴重なひと時となるでしょう。
代理散骨プラン

代理散骨プランでは、ご遺族そろっての散骨が難しい場合や、さまざま理由により乗船が難しい方・コストを抑えたい方に向け、弊社スタッフが代理で散骨を行うプランです。
散骨の様子を収めた写真や散骨証明書の発行など、ご遺族が安心してお任せできるサービス内容となっています。
また、散骨後のご遺骨をご自宅や身近な場所で管理・供養したい方に向けた手元供養品も多数そろえています。小さなポットからソウルジュエリーまでさまざまな種類がありますので、ぜひお好みの手元供養品をお選びください。
分骨の理由はさまざま お気持ちに合わせた供養を

「両家のお墓に埋葬したい」「散骨したい」「お墓が遠いから手元で供養したい」など、分骨を行う理由はさまざまです。
分骨後の供養方法の一つである散骨は、宗教的な制限や法律上の問題もありません。故人様の「自分の遺骨を大海原へ還し、自然と一体になりたい」という生前の希望や、ご遺族の意向に合う供養をするための手段として検討してみても良いでしょう。
シーセレモニーでは、海洋散骨や代理散骨、年忌法要クルージングなど、故人様を供養するためのさまざまなプランをご用意しています。
海洋散骨プランの詳細や予算、手元供養品など、疑問や気になる点があればいつでもご相談ください。後悔しないために理解を深め最善の方法を選択するお手伝いをいたします。