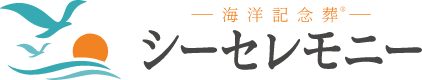お墓の場所が遠い場合や、ご遺骨を複数のお墓に納めたい場合に「分骨」を選択する方が増えています。これまで日本では「ご遺骨は一箇所に納める」ことが一般的だったため、分骨について詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、分骨の意味や具体的な手続きの流れ、さらには分骨に関するるトラブルを防ぐ方法などを詳しくご紹介します。分骨を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
分骨とは

分骨とは、ご遺骨を分けて納骨する方法です。たとえば、先祖代々のお墓が遠く頻繁に足を運べない場合、ご遺骨の一部を自宅近くのお墓に納めて供養します。また、お墓とは別に、ご遺骨を手元で供養する手元供養も分骨の一つです。
一度お墓に埋葬したあと、ご遺骨を取り出して分骨を行う場合は、事前に「改葬許可証」を発行してもらう必要があります。この許可証は、ご遺骨を埋葬している墓地がある市区町村の役場窓口で発行が可能です。
分骨は縁起が悪い?

日本では、これまでご遺骨は一箇所に納めることが通例だったため、分骨に否定的な意見も多いです。実際、ご遺骨を分けるという行為に対して、「縁起が悪いのでは?」「故人が成仏できないのでは?」と不安に思う方もいるのではないでしょうか。しかし、お釈迦様のご遺骨も分骨されて納められていることから、宗教的にも分骨は決して悪い方法ではないとされています。
ただし、分骨は心情的に受け入れがたいと感じるご遺族もいるため、分骨を行う際は慎重に検討し、話し合いを重ねることが重要です。
ご遺骨を分骨する方法

分骨はいつでも行うことができますが、タイミングによって手続きの仕方や流れに違いがあります。ここでは、分骨を行う時期ごとの手続きの違いや、分骨に至るまでの流れについて具体的に見ていきましょう。
手続き
分骨の手続きは、納骨前と納骨後で異なります。
納骨前に分骨する場合は、火葬場で「分骨証明書」の発行を依頼する必要があります。一方、納骨後に分骨する場合は、お墓を開けてご遺骨を取り出すため、墓地の管理者に「分骨証明書」を依頼します。
いずれの場合も、「分骨証明書」は分骨する数と同じ枚数が必要です。
また、手元供養としてご遺骨を自宅に保管する場合、将来的に納骨する可能性を考え、「分骨証明書」を発行してもらうことをおすすめします。
分骨の流れ

分骨までの流れも、納骨前と納骨後で違いがあります。それぞれの流れを簡単にご紹介します。
納骨前の場合
- 分骨する数と同じ骨壷を用意
- 火葬場に分骨証明書の発行を依頼
- 火葬場でそれぞれの骨壷にご遺骨を納める
- 分骨先の管理者に火葬証明書か分骨証明書を渡す
- 分骨先でそれぞれ納骨を行う
納骨後の場合
- お墓の管理者に分骨証明書の発行を依頼
- お墓からご遺骨を取り出す日程を決める
- 閉眼供養を行う
- 石材店や寺院に依頼して墓石を動かし、ご遺骨を取り出す
- 元のお墓にご遺骨を戻したあと、開眼供養を行う
- 分骨先の管理者に分骨証明書を渡す
- 分骨先でそれぞれ納骨を行う
分骨は、現在の状況に応じて行います。手続きや流れをよく理解し、慎重に進めることが重要です。
分骨によるトラブルを防ぐ3つのポイント

ご遺骨を分骨する際のトラブルを防ぐためには、いくつかの点に注意して慎重に進めることが大切です。ここでは3つのポイントについて解説します。
1.親族との十分な話し合い
分骨を進める際に最も重要なのは、親族との話し合いです。勝手に分骨を決めてしまうのではなく、故人様の遺志やご遺族の意向をしっかりと共有し、全員が納得する形で分骨を進めましょう。親族間で意見が分かれることもあるため、冷静に話し合うことが大切です。場合によっては、専門家に相談することも検討しましょう。
2.分骨証明書を保管しておく
ご遺骨を分骨する際には、「分骨証明書」が必要です。この証明書は、新たに納骨する際や改葬時に必要となるため、分骨が完了したあとも大切に保管しておきましょう。
3.適切な環境でご遺骨を管理する
分骨後にご自宅で手元供養を行う場合、保管環境には十分な注意が必要です。ご遺骨は湿気を吸いやすく、そのままだとカビが発生する恐れがあります。密閉性のある骨壺や専用の容器に入れ、湿気を避けて保管しましょう。また、直射日光が当たらない場所での保管が望ましいです。さらに、保管場所は定期的に清掃し、ご遺骨を大切に扱うことが求められます。
分骨後の供養方法

分骨したご遺骨は、それぞれのご希望に応じた方法で供養することができます。分骨後の代表的な供養方法を4つご紹介します。
新しいお墓へ納骨する
故人様のご親族が遠方に住んでいる場合や、異なる宗派・お墓に埋葬したい場合に選ばれる方法です。分骨したご遺骨を、新しく建立したお墓へ納めます。新しいお墓へ納骨する際は、「分骨証明書」のほかに「改葬許可証」も必要です。
納骨堂へ納骨する
納骨堂は、お墓を持たずにご遺骨を供養できる施設です。管理の負担が少なく、都市部でもアクセスしやすい場所であることが多いため、ライフスタイルに合わせて選ばれる供養方法の一つです。ご遺骨を納骨堂へ納める場合も、「分骨証明書」のほかに「改葬許可証」や「埋葬許可証」が必要となります。
手元供養する

分骨したご遺骨を自宅で供養する方法です。小さな骨壺に納めて仏壇に安置したり、ペンダントやアクセサリーに加工して身に着けたりできます。「いつでも故人様を偲び手を合わせられる」「精神的な支えとなる」などの理由から、選ばれることが多い供養方法です。
散骨する

分骨したご遺骨を自然に還す形で供養する方法です。散骨には、海洋散骨・里山散骨・空中散骨などがあります。「故人様が愛した自然に還したい」「お墓の維持・管理の負担を減らしたい」などの理由で、近年注目されています。
分骨後の供養方法には、ご遺族の意向や故人様の想いに応じた選択肢があります。最適な方法を選び、心を込めて供養しましょう。
供養方法についてのご相談はシーセレモニーへ

近年、少子高齢化の影響で、従来のお墓で供養する方法から、それぞれのライフスタイルに合わせた供養を選ぶ方が増えています。中でも「分骨」には、手元供養や近くの墓地へ改葬といった方法があり、故人様を身近に感じられる一方で、親族間で十分に話し合わないとトラブルにつながる恐れもあります。故人様の生前の希望やご遺族の意向を尊重し、慎重に選択することが大切です。

シーセレモニーでは、分骨後の供養方法の一つとして「海洋散骨サービス」を提供しています。そのほかにも供養に関するさまざまなお悩みをお聞きし、サポートを行っていますので、供養方法についてのご相談はシーセレモニーへおまかせください。